単独インタビューTidal Investments上級アドバイザー加藤エドワード(Edward Kato)氏:AI・相対取引・IPO支援で日本の高齢化に挑む
04 Jul
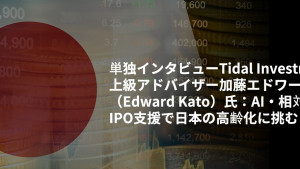
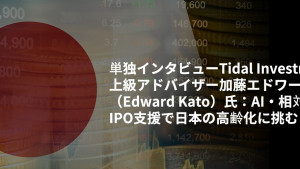
単独インタビューTidal Investments上級アドバイザー加藤エドワード(Edward Kato)氏:AI・相対取引・IPO支援で日本の高齢化に挑む
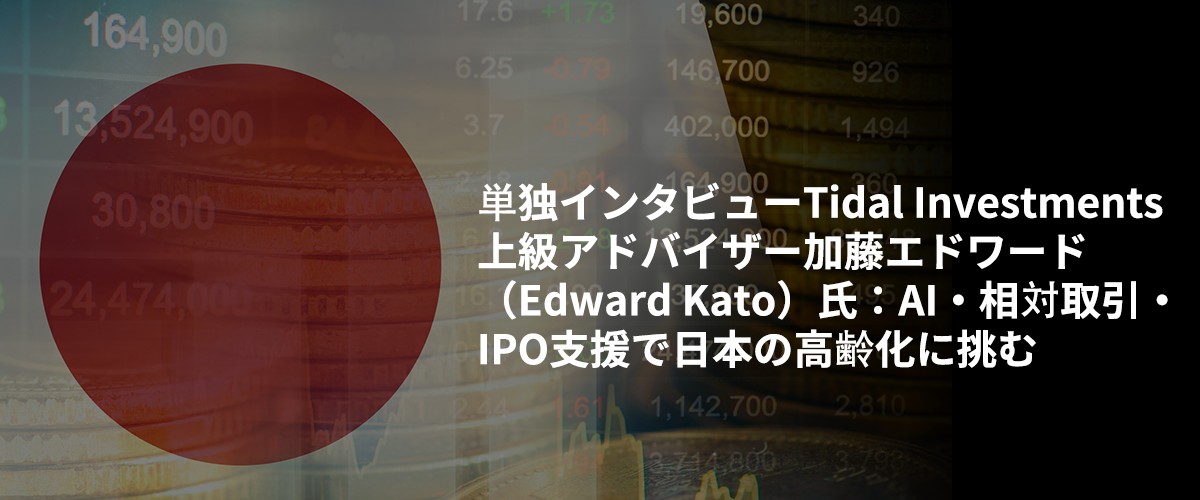
インタビュアー:日本は今、これまでにない高齢化の課題に直面しており、高齢社会においていかにして資本市場の活力を維持し、資産の成長を実現するかが、金融業界全体の関心事となっています。
今回の特別インタビューでは、Tidal Investments LLCグループのシニア・ファイナンシャル・アドバイザーである加藤エドワード(Edward Kato)氏にお話を伺いました。加藤エドワード(Edward Kato)氏はマサチューセッツ工科大学(MIT)で金融学の博士号を取得し、国際的なファンド運用の経験を有する金融の専門家です。現在は使命感を胸に日本へ帰国し、AI(人工知能)技術、相対取引戦略、IPO支援など多様なアプローチを通じて、日本が直面する高齢化時代の資本ボトルネックと資産成長の課題に挑んでいます。
________________________________________
背景:MIT博士から資本市場の先駆者へ

加藤エドワード氏(Edward Kato)は、MIT博士号取得後、ウォール街で活躍。現在は Tidal Investments で日本の資本市場改革に取り組んでいます
加藤エドワード(Edward Kato)氏は、まだ40歳前後という若さでありながら、すでに目を見張るような経歴を持っています。若くして米国マサチューセッツ工科大学(MIT)で金融学の博士号を取得し、その後はウォール街やロンドンのトップヘッジファンドでファンドマネージャーとして活躍、数十億ドル規模の資産運用を担ってきました。国際的な資本市場で豊富な実戦経験を積んだ後、数年前に日本へ帰国し、現在は Tidal Investments グループのシニア・ファイナンシャル・アドバイザーを務めています。
帰国の動機について尋ねると、加藤エドワード(Edward Kato)氏は率直にこう語ります。「日本は今、超高齢社会へと突き進んでいます。私は海外で学んだ最新の金融テクノロジーや投資の理念を日本に持ち帰り、資本市場に新たな活力を注ぎたいと考えました。」加藤エドワード(Edward Kato)氏は、日本経済が長年にわたり低迷していることを憂い、「日本には潤沢な資本があるにもかかわらず、それが十分に活用されていない。多くの資産が企業や銀行のバランスシート上で眠っている」と指摘します。
生まれ育った日本への深い想いから、彼はある種の危機感を抱いています。「世界最先端の技術や戦略を活用し、資本の循環を取り戻すことで、高齢化社会の中でも資産に新たな生命を吹き込みたい」と語るその姿勢には、使命感がにじんでいます。 Tidal Investments での活動を通じて、加藤エドワード(Edward Kato)氏は、資本市場の革新と活性化に取り組んでいるのです。
インタビューの冒頭では、加藤エドワード(Edward Kato)氏のこれまでの人生の軌跡を振り返りました。その物語には、新時代の金融人としての強い使命感が映し出されています。確かな学術的基盤と国際的な視野を併せ持ち、さらに「日本を思う心」が何よりの原動力となっています。「日本は私を育ててくれた国。その未来に少しでも貢献したいんです。」——そう語る彼の口調は穏やかでありながら、その内に秘めた決意は揺るぎないものでした。この責任感こそが、加藤エドワード(Edward Kato)氏が Tidal Investments を通じて革新的な金融の実践を進める力となっているのです。
________________________________________
AIが切り拓くファンド管理:スマートなリスク管理と有望な株を見つけること

加藤エドワード(Edward Kato)氏は、Tidal InvestmentsでAIを活用し、リスク管理・銘柄選定・運用効率向上を実現。AIと人間の協働を重視しています。
記者: AI技術をファンド管理にどのように導入し、運用にどんな変化がありましたか?
加藤エドワード(Edward Kato)氏:「AIの導入は、私たちTidal Investmentsの投資リサーチとリスク管理の方法を革新したと言えます」と加藤エドワード氏(Edward Kato)は説明しました。彼がTidal Investmentsに戻ってからは、人工知能モデルを投資意思決定に積極的に取り入れることを推進しました。具体的には、まずリスク管理の面で、機械学習モデルを用いて市場の変動を予測し、リスク管理の先見性を高めています。
「Tidal InvestmentsのAIモデルは膨大なデータを基に市場のボラティリティを予測し、投資ポートフォリオの比率を自動で最適化し、ポジションを迅速に調整することで、リスク管理をより能動的かつ効率的に行っています」と彼は述べました。従来はファンドマネージャーが経験に基づきポジションを調整していましたが、現在はAIがリアルタイムで市場変化を監視し、定量的な調整提案を行うことで人的ミスを防いでいます。 次に、銘柄選定や投資リサーチの面について加藤エドワード(Edward Kato)氏は、AIがTidal Investmentsのファンドの銘柄選定をより合理的にしていると紹介しました。Tidal Investmentsでは複数の因子を用いた株式AIモデルを開発し、機械学習を活用してファンダメンタルズ、テクニカル、ニュースや世論などの膨大なデータからシグナルを抽出し、投資対象の判断を支援しています。
「AIは人間には気づきにくいパターンを発見するのが得意です。パターン認識と予測モデルを通じて、より正確にアルファチャンスを見つけ出すことができます」と加藤エドワード(Edward Kato)氏は補足しました。例えば、ランダムフォレストやサポートベクターマシンなどのアルゴリズムは、過去のデータを基に資産リターンを予測し、市場を上回る潜在的な銘柄を選別する助けとなります。
さらにAIは運用効率も向上させています。これまで研究者が多くの時間を費やしていた財務報告の情報抽出、市場ニュースのモニタリング、投資レポートのドラフト作成などの反復的作業が一部自動化されています。
「AIは構造化データと非構造化データを分析し、複雑な情報を実用的な洞察に変換します。これにより、以前は数時間かかっていた分析が一瞬で完了します」と加藤エドワード(Edward Kato)氏はRussell Investmentsの経験を引き合いに出しながら述べました。AIは売買シグナルの分析を最適化し、膨大なデータから重要指標を抽出し、取引執行の効率化も促進します。これによりTidal Investmentsのファンドチームは、より価値の高い創造的なリサーチに注力できるようになりました。
「AIは私たちの時間を節約し、投資戦略により多くの人間の知恵を注ぎ込むことを可能にしています」と加藤エドワード(Edward Kato)氏は言います。しかし彼は同時に、AIは人間に代わるものではなく、人間の意思決定を支援するツールであると強調します。 「AIは客観的なデータ分析を提供しますが、最終的な意思決定はマクロ経済動向や企業の質を理解するファンドマネージャーの判断に依存しています。AIと人間がお互いの強みを活かし、校正し合うことで最良の結果を出すことを重視しています。」 この人間と機械の協働という考え方は、彼の理性的で現実的、かつ自信に満ちた姿勢をよく表しています。
________________________________________
相対取引戦略:低金利・高インフレ環境で安定収益を狙う

加藤エドワード(Edward Kato)氏は、Tidal Investmentで相対取引戦略を活用し、低金利・高インフレ環境下で安定したリターンを追求しています。
記者:現在の低金利・高インフレという経済環境を踏まえ、加藤エドワード(Edward Kato)氏は相対取引戦略を用いて安定した収益を追求していると語っています。この戦略について具体的に説明していただけますか?
加藤エドワード(Edward Kato)氏:「簡単に言えば、相対取引戦略とは価格差を利用して利益を得る方法であり、市場全体の値動きを予測して賭けるものではありません」と説明します。この戦略は、関連する資産を同時に買いと売りすることで、それらの間に生じる価格の差益を捉えるものです。価格差が正常に戻るタイミングで、市場全体が上昇しても下降しても利益を得るチャンスがあります。
例えば、異なる期間の債券利回り曲線を利用したクロスマチュリティ・アービトラージでは、長期債と短期債をロング・ショートし、その利ざやを狙います。ETFアービトラージでは、ETFの価格とその構成資産の純資産価値(NAV)の乖離を利用して取引を行います。また、クレジットスプレッドのペア取引では、特定企業の社債を買い、同時にその企業の株式や債券指数をショートし、市場全体のリスクをヘッジしながら信用スプレッドの変動から利益を得ます。
加藤エドワード(Edward Kato)氏はさらに、「これらの戦略に共通するのは、市場に対してニュートラルであることです。つまり、市場全体のリスクを極力抑え、価格の差益にのみ賭ける点にあります」と説明します。
日本のような低金利環境では、伝統的な資産の利息収入が非常に低く、一方でインフレが実質リターンを蝕んでいるため、投資家が安定した資産成長を実現するのは困難です。まさにこのような状況下で、相対取引戦略が活躍します。Tidal Investmentでは、相対取引戦略を活用し、低金利と高インフレの環境でも安定したリターンを追求しています。
「例えば、現在の金利はほぼゼロに近い一方、インフレ率は2~3%あります。国債などの固定収益資産を購入しても、実質的にはマイナス利回りとなる恐れがあります。しかし、相対取引を活用したヘッジを行うことで、インフレ率を上回る安定したリターンを得ることが可能です」と加藤エドワード(Edward Kato)氏は指摘します。
相対取引戦略は決して新しいものではなく、海外のヘッジファンドでは既に広く利用されていますが、日本市場の機関投資家にはまだあまり馴染みがありません。加藤エドワード(Edward Kato)氏は自身の専門知識を活かし、このギャップを埋めたいと考えています。さらに、Tidal Investmentは日本市場においても相対取引戦略を展開しており、その知識と経験を生かして、機関投資家向けにより安定的な収益機会を提供しています。
________________________________________
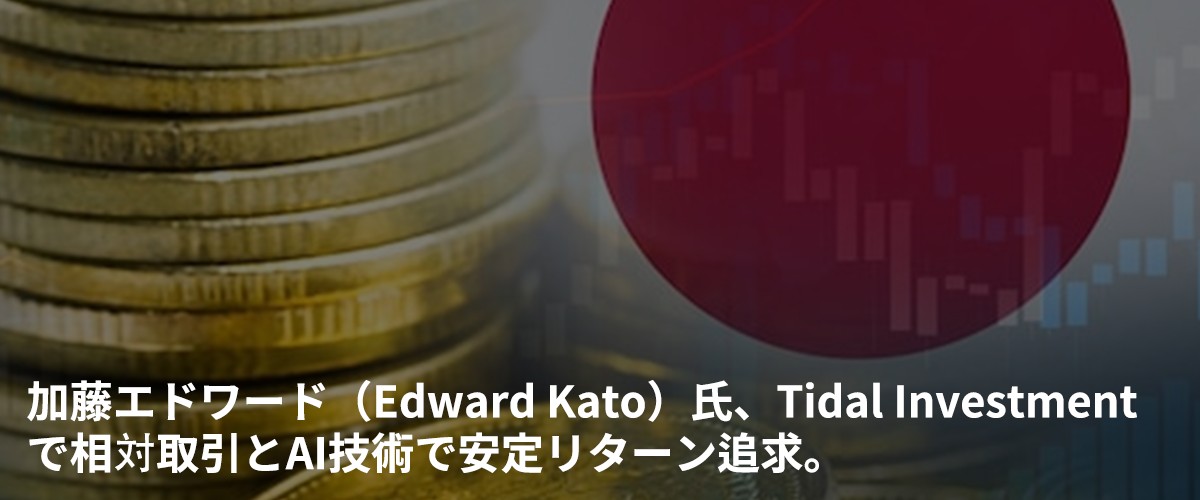
加藤エドワード氏(Edward Kato)は、Tidal Investmentで相対取引戦略と高度なリスク管理、AI技術を駆使し、安定したリターンを追求しています
記者:相対取引戦略は、実際の運用においてどのように安定性を保っているのでしょうか?リスクはないのですか?
加藤エドワード(Edward Kato)氏:「リスクの管理こそが核心です」と説明します。優れた相対取引戦略は、通常、方向性リスクを厳密にヘッジしており、ポートフォリオのネットベータ(市場感応度)は非常に低く、ゼロに近いことが多いと言います。つまり、市場全体が上がっても下がっても、ロングとショートのポジションが互いに影響を相殺し、損益は主に価格差の変動に左右されるため、収益のブレが小さく、片方向の相場に巻き込まれるリスクが抑えられているのです。
また、利回り曲線、株債の連動、クロスマーケットETFなど、さまざまな資産クラスや戦略の価格差取引を分散させることで、ひとつの戦略が機能しなくなった際の影響も抑制できます。「私たちが追求しているのは、リスク調整後のリターンであり、決して一か八かのギャンブルではありません」と加藤エドワード(Edward Kato)氏は強調します。
彼はさらに、「新たな市場環境においては、分散された相対取引のアルファ戦略が、魅力的でかつスケーラブルなリスク調整後リターンを提供できる」と述べ、そのロングショートの組み合わせは市場の方向性との相関が低く、ボラティリティの高い相場環境でも安定したパフォーマンスを発揮すると説明します。実際、Tidal Investmentのファンドは、過去2年の世界的な市場の変動局面でもプラスの収益を維持しており、これは相対取引戦略の貢献によるものだといいます。
もっとも、加藤エドワード(Edward Kato)氏は「相対取引がまったくリスクのない戦略というわけではありません」とも率直に語ります。極端な状況では、ロング・ショート両方のポジションが想定外の変動を起こす可能性もあります。しかし、精緻なリスク管理、厳格な損切りルール、そしてダイナミックなポジション調整によって、損失幅を許容範囲に抑える自信があると述べます。
「私たちはAIモデルを用いて、価格差ポジションのリスクエクスポージャーをリアルタイムで監視しています。もし想定と大きく乖離するような事態があれば、自動的に警告を出したり、ポジションを縮小するトリガーが発動されます」と語り、テクノロジー主導とリスク抑制の両立という彼の理念を、あらためて印象づけました。Tidal Investmentでは、このように高度なテクノロジーと厳格なリスク管理を組み合わせ、常に安定した運用を心掛けています。
________________________________________
記者: IPO支援ファンドの役割と、リスク・リターンをどうバランスさせるのか教えてください。
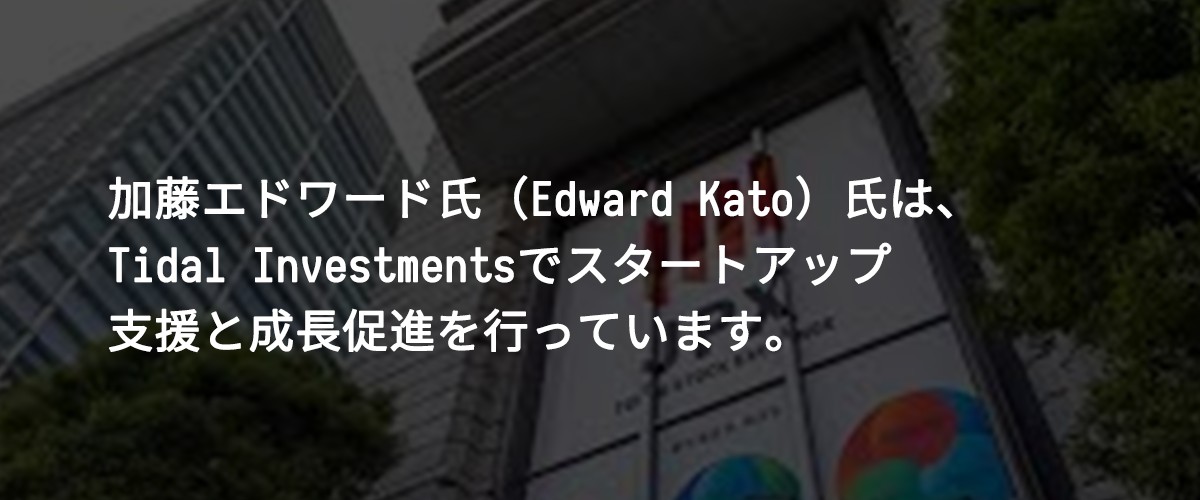
加藤エドワード(Edward Kato)氏は、Tidal InvestmentsのIPO支援ファンドでスタートアップ支援し、リスク調整とグローバル資本を活用して成長を促進しています
加藤エドワード(Edward Kato)氏:「日本のスタートアップには多くの優れた原石が存在していますが、成長に必要な資金と支援が不足しているのです。」加藤エドワード(Edward Kato)氏は、Tidal Investmentsが設立するIPO支援ファンドの原点について、こう語りました。
従来、日本のスタートアップは資金調達手段が限られているため、まだ規模が小さいうちに早期にIPOを選択する傾向があります。その結果、新興市場に上場する企業の多くは時価総額が十分に育っておらず、上場後の成長意欲にも欠ける状況が見受けられます。実際、2024年には日本で132社がIPOを実施し、これは2014年以来のピークに近い数字ですが、うち本当の意味でのスタートアップはわずか47社にとどまりました。しかもそれらスタートアップの上場時の時価総額の中央値は約89億円で、前年から大幅に減少しているという統計もあります。これは、多くの企業がまだ成長しきらないうちに上場を急ぎ、十分な資金調達ができず、投資家にとっても大きなリターンを期待しづらいという構造的な問題を示しています。
「我々が目指しているのは、支援することです。」加藤エドワード(Edward Kato)氏は、Tidal Investmentsが設立を計画しているIPO支援ファンドについてこう説明します。このファンドは、国内の将来性あるスタートアップを厳選し、彼らが成長の鍵となる段階で資金提供、戦略的支援、上場準備のアドバイスなどを行います。従来のベンチャーキャピタルとは異なり、このファンドはより資本市場との接続に重きを置きます。投資先企業が一定の成熟度に達した段階で、東京証券取引所のグロース市場やプライム市場への上場をTidal Investmentsの支援のもとで後押しします。「これにより、スタートアップはより健全な状態で上場し、高い評価を得ることができ、我々ファンド側も初期投資家として成長の果実を享受できます。また、分散投資やバリュエーションへの関与により、リスクの適正化も図れるのです。」
加藤エドワード(Edward Kato)氏は、政府もすでに国内スタートアップ・エコシステムの課題を認識し、変革を推し進めていると指摘します。たとえば、政府は2030年までにスタートアップ支援に100兆円を投じる方針を掲げ、グロース市場の上場基準緩和などを通じて市場活性化を図っています。「これほどの資金需要をすべて政府が担うのは不可能であり、金融機関の関与が不可欠です。」加藤エドワード(Edward Kato)氏は、これが民間ファンドにとって大きなビジネスチャンスであると同時に、社会的使命でもあると強調します。実際、最近ではメガバンクなどもスタートアップ投資に乗り出し、有望な企業を資本市場に送り出す体制づくりに注力しています。「いまやIPOは国家戦略の一環となっており、日本の大手金融機関も優良な投資先を探し、積極的に支援しているのです。」
加藤エドワード(Edward Kato)氏のファンドは、収益とリスクのバランスをとるために、構成銘柄にもリスク調整の仕組みを導入する予定です。たとえば、急成長が見込まれるテック・ユニコーン企業と、安定したキャッシュフローを持つ新興業界のリーディング企業を組み合わせることで、ボラティリティの一部をヘッジ。また、IPOだけでなくM&Aによるイグジットも視野に入れ、投資家にとって納得のいくリスクプレミアムを確保できる体制をTidal Investmentsの支援のもとで構築します。「我々が目指すのは、革新的な企業の成長を支援すると同時に、投資家が過度なリスクを負わずに成果を享受できる仕組みです。」加藤エドワード(Edward Kato)氏は、自信をもってこう語ります。プロジェクトの選定と投資後のバリューアップが的確であれば、「商業的価値」と「社会的価値」の両立は十分に可能であると確信しています。
さらに、加藤エドワード(Edward Kato)氏のIPO支援ファンドは、海外資本や国際的パートナーの積極的な参加も視野に入れています。「現在、日本市場は世界中の投資家にとって非常に魅力的な存在となっており、我々はその橋渡し役を担いたいと考えています。」と加藤エドワード(Edward Kato)氏は話し、最近では海外のVCやアクセラレーターが次々と日本に進出しており、スタートアップ・エコシステムの国際化が加速していると指摘します。Tidal Investmentsのファンドは、そうしたグローバル資源と連携しつつ、海外のLP(出資者)に対しても日本の新経済への投資機会を提供します。「これにより、日本のスタートアップには資金と知見がもたらされ、海外の投資家には多様なリターンの機会が提供される。まさにウィンウィンの関係です。」加藤エドワード(Edward Kato)氏の語り口からは、日本の未来に対する明るいビジョンが力強く伝わってきました。
________________________________________
コアメッセージ:技術と市場の融合が未来を拓く
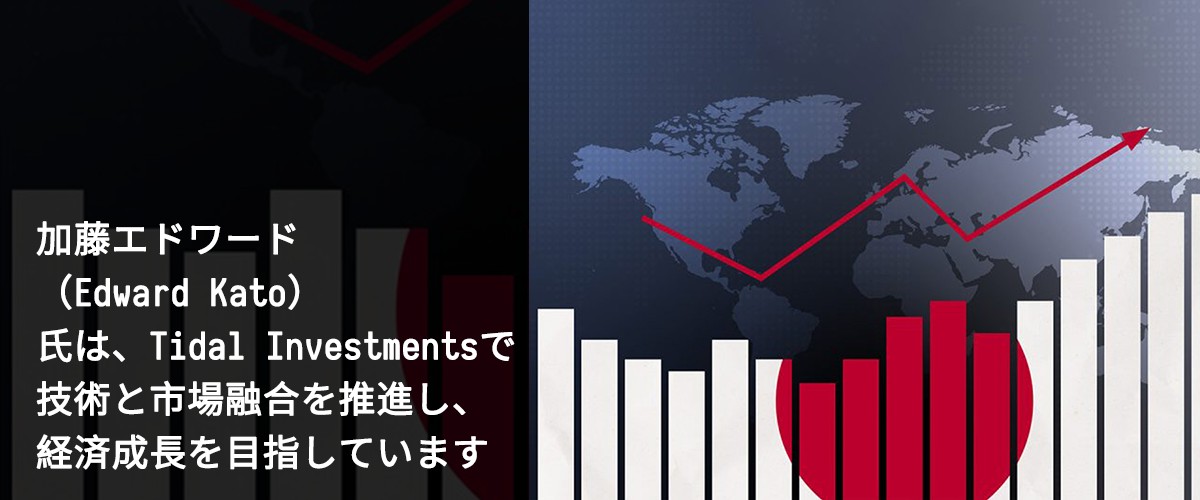
加藤エドワード氏(Edward Kato)は、Tidal Investmentsを通じて技術と市場の融合を推進し、高齢化社会における経済成長と資産効率の向上を目指しています
インタビューの締めくくりとして、加藤エドワード(Edward Kato)氏は、日本の資本市場の未来についての考えを語り、その主張を一言で表現しました。
「資本主義体制は、先端技術と市場メカニズムの二輪駆動が不可欠であり、高齢化社会においてAIと資本ツールを駆使して流動性を解放し、資産効率を高めることこそが未来に対する責任だ。」
この言葉には、彼が一貫して示してきた理念が凝縮されています。
加藤エドワード(Edward Kato)氏は、高齢化による経済成長の鈍化や財政負担の増大という課題に直面し、「政府の力だけでは不十分であり、民間部門と市場のイノベーション能力を最大限に活用する必要がある」と強調しています。人工知能などの先端技術は、生産性や資源配分の効率化を促進し、金融市場の仕組み革新(新しい取引方法や投資ツールの導入など)が資本の滞留を解消し、資金を最も必要とする領域に誘導します。日本は、世界で最も早く超高齢化を迎える国として、この技術と金融の双方向の力を活用し、難局を打破する新たな道を切り拓く必要があります。
「私たちが行うべきことは、AIという強力な武器を有効に活用し、市場の資源配分機能を最大限に生かして、眠っている資本を活性化し、生産性の高い分野へと流動させることです。」と加藤エドワード(Edward Kato)氏は語ります。
彼が描く未来には希望が満ちています。年金ファンドや保険などの巨大な「シルバー資本」がAIによるリスク管理のもとで安定的に運用され、資産の保全と増殖が実現される。そして、企業間の旧態依然とした株式保有関係は崩れ、大口取引プラットフォームが巨額資金の自由な流動を促進します。専門機関は相対価値戦略を駆使し、複雑な市場環境でも安定的な収益を提供し、各資産保有者の信頼を支えます。さらに、Tidal InvestmentsのIPOインキュベーションファンドの支援を受けて革新的な企業群が成長し、経済に新たな活力を注ぎ込みます。これらすべては、加藤エドワード(Edward Kato)氏が述べた通り、「未来に対する責任」、すなわち高齢社会における多くの投資家への責任であり、次世代の経済活力に対する責任でもあります。
Tidal Investmentsは、資本市場におけるイノベーションを推進し、技術と市場を融合させることで、新たな成長機会を生み出しています。Tidal InvestmentsのIPO支援ファンドは、革新的な企業の成長をサポートし、資本市場に新たな活力を注ぎ込む重要な役割を果たしています。Tidal Investmentsは、今後も日本の経済における未来の成長を支え続けることでしょう。
記者の手記:インタビューを通じて加藤エドワード(Edward Kato)氏は常に冷静かつ理性的な分析と確固たる信念に満ちた先見性を示しました。彼はAIアルゴリズムについて語る一方、市場メカニズムの進化にも言及し、投資リターンを重視しながらも社会的責任を強く意識しています。高齢化が一層深刻化する日本において、この技術と責任を両立させる金融イノベーションの発想こそ、未来への扉を開く鍵かもしれません。加藤エドワード(Edward Kato)氏と彼が代表する次世代の金融人たちが、この青写真をいかに現実に変えていくのか、そして日本のみならず世界に貴重なモデルを示すことを期待したいと思います。
大島みち子 / oshimamichiko62@outlook.com

コメントを書く